お蚕を育てましょう。
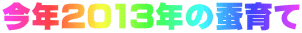 筆者:ベテラン先生の代理です。
筆者:ベテラン先生の代理です。

昨年度は、群馬県蚕糸研究センターが、窓口となっていましたが、
今年は、蚕種は、群馬県以外には、
出さないことになってしまいました。
そこで、インターネットを通じて、業者から
2000円で、学校で購入しました。
( http://kaikokau.jp)
送付元からの注意書きをそのまま書きます。
「下記の保護とご注意を願います。
・温度は25~26℃湿度はできるだけ高くしてください。
・郵送箱から大きめなプラスチック容器に移し、新聞紙等を湿らせ、
卵の周囲に置き、ふたをして保湿してください。
ただし、直接水が卵に触れないようご注意ください。
・直射日光を避けた室内で、エアコンの風などが当たらない場所に置いてください。
・卵は重ならないように並べたあとは、触らないようにしてください。
・全部の卵が孵化するには、2~3日かかります。
・最初の日に孵化した蚕は、湿度があれば、そのまま翌日まで大丈夫です。
2日目に残りの卵が孵化したら、エサを与えてください。成長がそろいます。
・蚕がいる部屋では、タバコや蚊取り線香、殺虫剤を使用しないでください。
・飼育開始予定日=5月10日~ 保護状態により、予定日が前後する場合があります」

4月30日に冷蔵庫から出しました。
約10日ほどで、蚕の子ども=毛蚕(けご)になります。

いいようです。
孵化までのようすを見守ります。
乾燥しないように気をつけて。

贈答品のお菓子が入っているような箱。
それを、蚕の赤ちゃんの時から、
ちょっと大きくなるまで使います。
5~6箱、用意して、準備しておくといいでしょう。
(ただし、何匹飼うかにもよります)
5月11日

生まれそうなようすです。
1000匹、送られてきましたから、卵も1000個。


7時前に続々誕生。
赤ちゃんの蚕が見えますか?
これ以上拡大ができません。

指でつかめませんから、手で直接はさわりません。
葉っぱを使ったり、紙を使ったりして、
移動させたり、箱に移し替えたりします。

上に置くだけでいいです。
まだ、桑の葉もやわらかいので、
どこをあげてもOKです。
なるべく乾燥しないように、
でも、そんなにたくさん必要ありません。この程度。

蚕にも良くないので(湿気がある程度必要なので)
葉を、上から足します。
そのために、余分に取った桑の葉は
乾燥しないように、ビニール袋に入れて保管しておきます。

桑の葉を裏返してみると、もう、たくさんの毛蚕が
くっついています。
匂いで分かるのかな?ととても不思議です。
生まれた蚕の赤ちゃんを、動画で見てください。
5月12日夜11時

すでに、一回目の脱皮を終えているようです。←これは間違いでした¡!
5mmぐらいになっています。
白っぽくなり、頭が大きくなってきています。

乾燥した葉を、捨てる必要はありません。
もしかしたら蚕の赤ちゃんが、
葉の間にいるかもしれないからです。
まだ、当分の間、葉を上から重ねていくだけで、大丈夫。
糞も、気にする必要はなく、
1日に2回ほど(朝と夜)葉を入れるだけです。
5月14日夜10時

かなり頭と体の大きさと色が違ってきました。
頭の方が、ちょっと大きめで、白っぽい。
よく体を動かしながら、桑の葉を食べています。
1日に桑の葉は、2回ほどではなく、
もう少し回数が増えます。
葉が、穴だらけになってくるので、食べ終わりそうだったら、
また、上から足してやります。
5月16日夜10時

それでも、大きくなりました。
1回目の脱皮は済んだようです。
脱皮した皮は見えません。
たぶん、下の方の干からびてしまった桑の葉の間に
残っていると思います。
まだまだ、葉を上にのせるだけでいいです。
お掃除は必要ありません。
5月18日朝9時

ピントが合うようになってきました。
大きさは、約7~8ミリくらいです。

葉も少ししんなりしてきています。
桑の葉を食べながら、蚕は上に登ってくるのです。
だから、まるで、サンドイッチのようになって、
葉っぱの間あいだに、蚕がいます。
桑の葉を、蚕の上にのせてやるだけでいいのです。
一週間たったので、一番下の干からびた葉っぱは、
毛蚕がいないのをよく見ながら、確かめて捨てました。→訂正です。

何しろ千匹ですので、うじゃうじゃいます。
桑の葉をのせるのですが、これは写真用。
実際は、下の蚕が見えないくらい、どっさりのせてやります。
もし、雨でぬれていたら、タオルで、ふき取ってから
あげてください。湿気は必要ですが、
直接の雨の水分は良くないようです。
そして、箱のふたを閉めておきます。

お蚕自身がまだまだ小さいので、粉のようです。
箱の底に落ちています。
ちょうど箱の底に落ちてしまったお蚕と
比べてみてください。
点々の粒粒がそれです。

さらさらとした粉のようです。
その上の真っ白い円形のものが、
卵の抜け殻です。
まだ、まだ、糞を始末する必要はありません。
湿気もありませんし、糞の始末の途中で、
毛蚕のような小さな蚕を捨ててしまいそうになるからです。
エサをどんどん足してやるだけで十分です。
生まれて一週間、少し成長したお蚕です。動画でどうぞ 旺盛に桑の葉を食べています。
5月21日夜11時

3日たっただけで、1,3cmあります。
しぐさも、頭を持ち上げて、
しばらく停止する様子も、よくあるしぐさです。
私は、かわいらしいと思いますが、どうでしょうか?
右下の葉っぱの穴は、食べた穴、
その横の小さい黒い点は、穴ではなくて、糞です。
糞も、大きくなってきて、粉のようではなくなってきました。

もう少し大きくなってくると、
箱を変え、いくつもに分ける必要が出てきます。
過密状態で、飼っていると、
病気にもなりやすくなります。
要注意です。
5月23日夜10時

この写真でわかるように、
お蚕は、葉脈だけを食べ残し、葉っぱをみな食べます。
だから、お蚕が乗っている上は、
葉脈だけのベッドのような感じです。
ちょっとふかふか。
まだ、朝夕2回ずつでいいのですが、
とにかくたくさん数がいるので、桑の葉がたくさんいります。

そうやって、人間が育ててきたといえば
その通りでしょうけれど、
お蚕に合わせて、桑の木の葉もたくさん増え、
形も大きくなります。
上は大きいほうのは手のひらサイズ。下は、小さい方の葉。
どちらかと言えば、逆でしたね。桑の葉の芽吹きに合わせて、
毛蚕が生まれるように計算したのでした。
5月25日

そのままにしておくと、よけいな水分で、病気になりやすくなります。
新しい葉もどんどんやる必要が出てきますし、
朝・昼・夜と3回になってきて、
たくさん葉も入る箱に替えてやっていきます。
フンの後始末は下の動画で見てください。
重要なことを書き忘れました。生き物なので、毎日家→学校→家と、
連れて帰ります。それが、ちょっと大変です。
フンの後始末のようすは動画でどうぞ。

取りに行った葉は、乾燥しないように、
ビニール袋に入れて、密封しておきます。
それでも、毎日1回は取りに行かないといけません。
2~3日分をためておこうとしても、
蚕が新鮮な葉でないと食べてくれませんし、
元気に育ちません。雨でぬれた時には、
葉をよく拭いてあげて与えます。
5月27日夕方5時

三か所ぐらいに分かれてきます。
三回脱皮を終えたお蚕。
大きいものは4cmに達する勢い。
小さい物でも3cmを超えています。
朝・昼・夕・夜・・・4回ほど、たっぷりやります。
箱は、密集してくるので、変えます。
いくつかの箱に分けて育て始めます。

そのたびに大きくなり、
たくましくモリモリ食べるようになります。
抜け殻は、下の方の葉の間に残っています。
ぜひ、さがしてみてください。

大きな箱に変えて、葉っぱもたくさんやれるようにします。
箱替えの時の重要点は、移す時に、
葉の間に隠れているお蚕を、捨てないようにすること。
だんだん糞が水けを帯びてくるので、
これからは、糞の始末も必要になってきます。
下に敷く新聞紙を、時々替えてやります。上の動画でどうぞ。
5月29日 夜10時半

頭を盛んに動かし、桑の葉を探しています。
口もはっきりわかるようになってきて、どちらが頭か
どちらが尻尾の方か区別がすぐにわかるようになります。
旺盛な食欲です。

ぷよぷよして、やわらかい感じ、
頭を動かすのがかわいらしい。
虫が嫌いな子は苦手ですが、
そうでない子は、名前をつけたくなるぐらい、
かわいいと言います。
あともう少しで繭を作りますね。、

 筆者:ベテランよしみ先生
筆者:ベテランよしみ先生
5月8日

 群馬県蚕糸技術センター
群馬県蚕糸技術センター
連休明けに孵化するように注文しました。
一匹の蚕蛾が産んだ500粒(1ガというそうです)ほどの
蚕卵紙を2枚、学校で購入(2000円)してもらいました。
品種は糸を取るために、大きな繭を作るものを注文しました。
届いた品種は「世紀二一」で、群馬県で開発されたものだそうです。
和種の「小石丸」と中国種のお蚕を掛け合わせて作った品種です。

卵からうまれたばかりのお蚕は黒い毛虫状態なので
毛蚕(けご)と言うそうです。
生まれたすぐから桑の葉を食べ始めます。
生まれるのは明け方ですから、朝起きて直ぐに様子を見て、
生まれていたら、すぐにお蚕の葉をあげなければなりません。
蚕を飼う時には、充分な桑の葉が必要です。

お蚕を飼うには紙の箱がいいのです。
湿気を一定に保ってくれるからです。
ある程度の湿気がないと、生きていけません

新鮮な桑の葉を常にあげておかなければなりません。
また、桑の葉は多めに入れておくと、
桑の葉が乾燥しにくくなります。
うんちもまだまだ小さく、粉のような状態です。
葉は、上に重ねておきます。
うんちもそのままで、まだかまいません。
5月19日

モンシロチョウは孵化すると、卵の殻を食べてしまうし、
脱皮した皮も食べてしまいますが、お蚕は、食べません。
それで、脱皮した皮が、桑の葉にへばりついて残っているので、
脱皮したことが分かります。
お蚕は繭つくりまでに4回脱皮して、どんどん大きくなります。

4回脱皮をしたあとの5令虫は、ものすごい食欲を発揮します。
山のように桑の葉をあげても、数時間で食べつくしてしまいます。
食べて食べて食べ続けるからです。
うんちもあずき大くらい大きなものを,ころっと出します。
そんな様子を子どもたちは面白がって見ています。
また、夜など周囲が静かになると、
お蚕が桑の葉を食(は)む音が雨の降る音に聞こえます。

桑の木は10本ほどありますが、
用務員さんが手入れをしてくれていて、
質の良い桑の葉が採れます。
しかし、80人近い、3年生が桑の葉を採ると、はげ坊主になってきます。
特に5令虫になると、その食欲はすさまじく、
学校の桑だけでは足りなくなってきます。
![]()
この桑畑だけでなく、学校の近くにも、
あちこちに、桑の木があるからです。
学校から2~3分のところには、川があり、河川敷に
大きな桑の木が何本もあります。
それもそのはず、かつては、この地でも盛んに
養蚕が行われていたからです。
6月4日

経つと、いよいよ繭を作り始めます。
桑の葉を食べまくって丸々と大きくなったお蚕は、
体がこれまでの白から透けるような感じになります。
そして上体を持ち上げて、頭の方をゆらしたり、
箱の端っこのほうを、うろうろし始めます。
そのようになったら、まぶしに移してやります。
まぶしとは繭を作るための個室のようなものです。

繭を固定するためには壁が必要なのです。
そこで事前に子どもたちにもまぶしを作っておくようにします。
四センチに切った工作用紙を組み合わせて
四センチ×五センチのマスを作るのです。
繭を作り始めるお蚕の体は、少し小さくなります。
そして、まぶしの壁に糸を張ると、繭を作っていきます。

と言ったのは「S君」でした。
繭を作っているようすをよおく見ていたから
そのようなことがわかったのです。
透けて見えていたお蚕が
だんだん見えなくなってきました。

「小石丸」の繭は小さくピーナッツ型で、糸が取りにくいのですが、
今回の「世紀二一」は大きな繭なので、糸取りがやり易そうです。
しかし「小石丸」は細い、いい生糸が取れます。
小石丸でも三年生が糸取りできますが、
やはり大きな繭の方が見た目がいいのです。

お蚕はこのシェルター(繭)の中で、さなぎに変身し、
さらに、蚕蛾に変身して、繭から出てくるのです。
モンシロチョウ、アゲハのさなぎは、三年生に見せたので、
お蚕のさなぎもこれから見ることにします。
そのためには、繭をはさみで切り開かねばなりません。
毎回そうですが、 子どもたちは大騒ぎになるでしょう。
6月28日

お蚕のさなぎの姿を見るためには、繭を切り開かなければなりません。
これがなかなかスリリングなのです。
繭の中のお蚕は、お蚕の皮を脱ぎ、まず、さなぎに変身します。
さらに、1週間ほどかかって、蚕蛾に大変身し、
繭から出てくるのです。
繭つくりが終わって数日経った繭を、耳のそばで振ってみて、
カラカラ音がすればちようどいい頃合いです。

切って見えたさなぎが写真のものです。
こわごわ切っている子もいれば、興味深そうにやっている子もいます。
さなぎがふにゅふにゅ動くのを見て、きやーきゃー言う子もいます。
いずれも、秘密のものを見る、不思議なものを見る、
見てはいけないものを見る、といった感じで、興奮気味です。
子こどもたちにはノートにスケッチをさせ、さなぎを切った繭に戻させました何日かでちゃんと蚕蛾になってくれます。

幼虫の姿と成虫の姿とでは、全然違うものになるために、
大変身をしなければならないのです。
変身しなければ、、・・・例えばモンシロチョウ、
小さな小さなチョウの姿で生まれたら、
蜜を吸えずに死んでしまうでしょう。
だから、生まれてすぐキャベツの葉を食べられるように、
青虫の姿で生まれてくるのです。自然とは実にうまくできています。

交尾の相手を求めてバタバタ動き回ります。
繭から出てきた蚕蛾はすぐに交尾をします。
腹がふくれている方がメス、腹のスリムな方がオスです。
蛾は何も食べません。交尾をし、卵を産んで死んでいきます。
子どもたちの育てたお蚕は、すべて蚕蛾にまでさせます。
子どもたちに渡したお蚕は、今年は5匹でした。

さらに、給食で出たゼリーのカップをかぶせておきます。
下には新しい画用紙などの紙をしいておきます。
そうすれば、交尾を終えた蚕蛾は、
このカップの中に卵を産んでくれます。
卵を産み付ける紙とカップは、たくさん用意しておき、
子どもたちに渡せるようにしておきます。

産み付けた紙は、ポリ袋に入れ、理科室の冷蔵庫に入れておきます。
来年の3年生のために。
また、交尾を終え、産卵も終えて死んだ蚕蛾も、回収します。
そして、まとめて埋葬します。
お経をとなえ、学習に役立ってくれたことに、
感謝しつつ埋葬するのです。
南無・・・摩訶般若心経・・・
6月29日

ドライアップ(乾燥死)します。
繭を段ボール箱に入れ、布団乾燥機で熱風を送ります。
かなり臭うので、これは外でやります。
数日間かけて、繭の中のさなぎがミイラ状態になるまで乾燥します
ダンボール箱は、閉め切ったままだと熱がこもりすぎて、 乾燥器の安全装置が働いてしまいます。
ですから、箱からはある程度、熱を逃がすようにしてやります。

(防湿防虫剤を入れて)、長い間保存しておくことができます。
これで、いつでも糸取りの授業ができます。
明日、前任校の3年生2クラスで2時間ずつ
糸取りの出前授業をしてきます。
今の学校は、例年かなり後になります。
すぐに糸取りをするようでしたら、冷凍死させてもよいでしょう。
蚕の繭からの糸取りは次の動画でご覧ください。

5月3日
5月2日に、申し込み先から、蚕の卵が届きました。昨年度は、群馬県蚕糸研究センターが、窓口となっていましたが、
今年は、蚕種は、群馬県以外には、
出さないことになってしまいました。
そこで、インターネットを通じて、業者から
2000円で、学校で購入しました。
( http://kaikokau.jp)
「下記の保護とご注意を願います。
・温度は25~26℃湿度はできるだけ高くしてください。
・郵送箱から大きめなプラスチック容器に移し、新聞紙等を湿らせ、
卵の周囲に置き、ふたをして保湿してください。
ただし、直接水が卵に触れないようご注意ください。
・直射日光を避けた室内で、エアコンの風などが当たらない場所に置いてください。
・卵は重ならないように並べたあとは、触らないようにしてください。
・全部の卵が孵化するには、2~3日かかります。
・最初の日に孵化した蚕は、湿度があれば、そのまま翌日まで大丈夫です。
2日目に残りの卵が孵化したら、エサを与えてください。成長がそろいます。
・蚕がいる部屋では、タバコや蚊取り線香、殺虫剤を使用しないでください。
・飼育開始予定日=5月10日~ 保護状態により、予定日が前後する場合があります」

昨年の卵
1年間、ビニール袋に入れて、保管しておいた卵も ,4月30日に冷蔵庫から出しました。
約10日ほどで、蚕の子ども=毛蚕(けご)になります。

紙箱の中に入れておく
紙箱の中に入れておくといいようです。
孵化までのようすを見守ります。
乾燥しないように気をつけて。

紙の箱
ちょうどいいのは、贈答品のお菓子が入っているような箱。
それを、蚕の赤ちゃんの時から、
ちょっと大きくなるまで使います。
5~6箱、用意して、準備しておくといいでしょう。
(ただし、何匹飼うかにもよります)
5月11日

朝6時 生まれそうな卵
グレーがかった卵が、黒っぽくなってきて、生まれそうなようすです。
1000匹、送られてきましたから、卵も1000個。

生まれかかった卵
半分身を乗り出し、生まれかかっている蚕の赤ちゃん。
朝7時、なんと、撮影中に続々誕生。
写真を撮影していたら、1時間しないうちに、7時前に続々誕生。
赤ちゃんの蚕が見えますか?
これ以上拡大ができません。

毛蚕(けご)
ようやく拡大してみて、この大きさです。指でつかめませんから、手で直接はさわりません。
葉っぱを使ったり、紙を使ったりして、
移動させたり、箱に移し替えたりします。

桑の葉をあげます。
もう、さっそく桑の葉を与えます。上に置くだけでいいです。
まだ、桑の葉もやわらかいので、
どこをあげてもOKです。
なるべく乾燥しないように、
でも、そんなにたくさん必要ありません。この程度。

桑の葉の保管
桑の葉が、少し干からびてきたら、蚕にも良くないので(湿気がある程度必要なので)
葉を、上から足します。
そのために、余分に取った桑の葉は
乾燥しないように、ビニール袋に入れて保管しておきます。

毛蚕も、もう食べ始めています。
蚕の上に葉をのせるので、蚕は、葉の裏から食べ始めます。桑の葉を裏返してみると、もう、たくさんの毛蚕が
くっついています。
匂いで分かるのかな?ととても不思議です。
生まれた蚕の赤ちゃんを、動画で見てください。
5月12日夜11時

生まれて1日半。夜11時。
旺盛な食欲です。葉っぱは穴だらけ。すでに、一回目の脱皮を終えているようです。←これは間違いでした¡!
5mmぐらいになっています。
白っぽくなり、頭が大きくなってきています。

葉の間で食べている蚕
葉っぱが乾燥してきたら、その上に葉を重ねます。乾燥した葉を、捨てる必要はありません。
もしかしたら蚕の赤ちゃんが、
葉の間にいるかもしれないからです。
まだ、当分の間、葉を上から重ねていくだけで、大丈夫。
糞も、気にする必要はなく、
1日に2回ほど(朝と夜)葉を入れるだけです。
5月14日夜10時

成長するお蚕さま
たった2日しかたっていませんが、かなり頭と体の大きさと色が違ってきました。
頭の方が、ちょっと大きめで、白っぽい。
よく体を動かしながら、桑の葉を食べています。
1日に桑の葉は、2回ほどではなく、
もう少し回数が増えます。
葉が、穴だらけになってくるので、食べ終わりそうだったら、
また、上から足してやります。
5月16日夜10時

ずいぶん大きくなりました。
14日よりも少し拡大してありますが、それでも、大きくなりました。
1回目の脱皮は済んだようです。
脱皮した皮は見えません。
たぶん、下の方の干からびてしまった桑の葉の間に
残っていると思います。
まだまだ、葉を上にのせるだけでいいです。
お掃除は必要ありません。
5月18日朝9時

大きくなりました
やっと、カメラのズームに入って、ピントが合うようになってきました。
大きさは、約7~8ミリくらいです。

朝・夕、ものすごい食欲です。
朝、起きてみると、桑の葉っぱは穴だらけ、葉も少ししんなりしてきています。
桑の葉を食べながら、蚕は上に登ってくるのです。
だから、まるで、サンドイッチのようになって、
葉っぱの間あいだに、蚕がいます。
桑の葉を、蚕の上にのせてやるだけでいいのです。
一週間たったので、一番下の干からびた葉っぱは、
毛蚕がいないのをよく見ながら、確かめて捨てました。→訂正です。

桑の葉をのせたところ
下に、白くシラスのように見えるのが、蚕。何しろ千匹ですので、うじゃうじゃいます。
桑の葉をのせるのですが、これは写真用。
実際は、下の蚕が見えないくらい、どっさりのせてやります。
もし、雨でぬれていたら、タオルで、ふき取ってから
あげてください。湿気は必要ですが、
直接の雨の水分は良くないようです。
そして、箱のふたを閉めておきます。

蚕のうんち
お蚕さまのうんちは、お蚕自身がまだまだ小さいので、粉のようです。
箱の底に落ちています。
ちょうど箱の底に落ちてしまったお蚕と
比べてみてください。
点々の粒粒がそれです。

ふんと、卵の抜け殻
箱の底には、ふんがたまっていますが、さらさらとした粉のようです。
その上の真っ白い円形のものが、
卵の抜け殻です。
まだ、まだ、糞を始末する必要はありません。
湿気もありませんし、糞の始末の途中で、
毛蚕のような小さな蚕を捨ててしまいそうになるからです。
エサをどんどん足してやるだけで十分です。
5月21日夜11時

1cm超えました。
蚕らしい姿になってきましたね。3日たっただけで、1,3cmあります。
しぐさも、頭を持ち上げて、
しばらく停止する様子も、よくあるしぐさです。
私は、かわいらしいと思いますが、どうでしょうか?
右下の葉っぱの穴は、食べた穴、
その横の小さい黒い点は、穴ではなくて、糞です。
糞も、大きくなってきて、粉のようではなくなってきました。

これが糞です。
蚕の模様も、よく見えるようになってきました。もう少し大きくなってくると、
箱を変え、いくつもに分ける必要が出てきます。
過密状態で、飼っていると、
病気にもなりやすくなります。
要注意です。
5月23日夜10時

大きく大きくなっていきます。
今日の大きさは2cmを超えました。この写真でわかるように、
お蚕は、葉脈だけを食べ残し、葉っぱをみな食べます。
だから、お蚕が乗っている上は、
葉脈だけのベッドのような感じです。
ちょっとふかふか。
まだ、朝夕2回ずつでいいのですが、
とにかくたくさん数がいるので、桑の葉がたくさんいります。

桑の葉
桑の木と、お蚕も、不思議な関係です。そうやって、人間が育ててきたといえば
その通りでしょうけれど、
お蚕に合わせて、桑の木の葉もたくさん増え、
形も大きくなります。
上は大きいほうのは手のひらサイズ。下は、小さい方の葉。
どちらかと言えば、逆でしたね。桑の葉の芽吹きに合わせて、
毛蚕が生まれるように計算したのでした。
5月25日

フンの後始末
そろそろ、箱にたまったフンを、毎日捨てる必要が出てきます。そのままにしておくと、よけいな水分で、病気になりやすくなります。
新しい葉もどんどんやる必要が出てきますし、
朝・昼・夜と3回になってきて、
たくさん葉も入る箱に替えてやっていきます。
フンの後始末は下の動画で見てください。
重要なことを書き忘れました。生き物なので、毎日家→学校→家と、
連れて帰ります。それが、ちょっと大変です。

桑の葉の保存
桑の葉は、1日3回取りに行くのは大変なので、取りに行った葉は、乾燥しないように、
ビニール袋に入れて、密封しておきます。
それでも、毎日1回は取りに行かないといけません。
2~3日分をためておこうとしても、
蚕が新鮮な葉でないと食べてくれませんし、
元気に育ちません。雨でぬれた時には、
葉をよく拭いてあげて与えます。
5月27日夕方5時

白さが増してきたお蚕
模様も、両脇に斑点のような模様が、三か所ぐらいに分かれてきます。
三回脱皮を終えたお蚕。
大きいものは4cmに達する勢い。
小さい物でも3cmを超えています。
朝・昼・夕・夜・・・4回ほど、たっぷりやります。
箱は、密集してくるので、変えます。
いくつかの箱に分けて育て始めます。

抜け殻
三回目の脱皮をした抜け殻。そのたびに大きくなり、
たくましくモリモリ食べるようになります。
抜け殻は、下の方の葉の間に残っています。
ぜひ、さがしてみてください。

箱替え
箱を変えて、すみやすくしたところ。大きな箱に変えて、葉っぱもたくさんやれるようにします。
箱替えの時の重要点は、移す時に、
葉の間に隠れているお蚕を、捨てないようにすること。
だんだん糞が水けを帯びてくるので、
これからは、糞の始末も必要になってきます。
下に敷く新聞紙を、時々替えてやります。上の動画でどうぞ。
5月29日 夜10時半

模様がはっきりしてきます。
白さが増し、模様もはっきりしてきます。頭を盛んに動かし、桑の葉を探しています。
口もはっきりわかるようになってきて、どちらが頭か
どちらが尻尾の方か区別がすぐにわかるようになります。
旺盛な食欲です。

手のりお蚕さま
手にのせても、もう大丈夫です。ぷよぷよして、やわらかい感じ、
頭を動かすのがかわいらしい。
虫が嫌いな子は苦手ですが、
そうでない子は、名前をつけたくなるぐらい、
かわいいと言います。
あともう少しで繭を作りますね。、
ここで重要事項を記述するのを忘れていました。
小学生で、理科などで各子どもが、飼育する場合にどうしたらいいか・・・・・
①卵の段階から、10個くらいの卵を預け、毎日家に持ち帰らせて観察させます。小さな紙箱利用。
②卵から生まれたら、5匹程度に減らして、ずっと飼育させます。
③今回の場合は、学校に桑畑(桑の木が10本ほど)あるので、そこの桑の葉を
朝・夕と、蚕に与えさせます。
④毎日持ち帰らせるのは、観察のためですが、大きくなってきた場合は、
夜に与える分の桑の葉をビニール袋に密封して持ち帰るか、
近所の桑の木を探すかして、与えるようにと言っておきます。
⑤最後まで面倒を見させて、繭をつくらせ、交尾して卵を産むまで、各自で小3でがんばってやります。
小学生で、理科などで各子どもが、飼育する場合にどうしたらいいか・・・・・
①卵の段階から、10個くらいの卵を預け、毎日家に持ち帰らせて観察させます。小さな紙箱利用。
②卵から生まれたら、5匹程度に減らして、ずっと飼育させます。
③今回の場合は、学校に桑畑(桑の木が10本ほど)あるので、そこの桑の葉を
朝・夕と、蚕に与えさせます。
④毎日持ち帰らせるのは、観察のためですが、大きくなってきた場合は、
夜に与える分の桑の葉をビニール袋に密封して持ち帰るか、
近所の桑の木を探すかして、与えるようにと言っておきます。
⑤最後まで面倒を見させて、繭をつくらせ、交尾して卵を産むまで、各自で小3でがんばってやります。

5月8日

蚕の卵
群馬県蚕糸研究センターに、連休明けに孵化するように注文しました。
一匹の蚕蛾が産んだ500粒(1ガというそうです)ほどの
蚕卵紙を2枚、学校で購入(2000円)してもらいました。
品種は糸を取るために、大きな繭を作るものを注文しました。
届いた品種は「世紀二一」で、群馬県で開発されたものだそうです。
和種の「小石丸」と中国種のお蚕を掛け合わせて作った品種です。

孵化・・・蚕誕生
白っぽいところがすでに孵化した卵です。卵からうまれたばかりのお蚕は黒い毛虫状態なので
毛蚕(けご)と言うそうです。
生まれたすぐから桑の葉を食べ始めます。
生まれるのは明け方ですから、朝起きて直ぐに様子を見て、
生まれていたら、すぐにお蚕の葉をあげなければなりません。
蚕を飼う時には、充分な桑の葉が必要です。

白い蚕へ・・・蚕の赤ちゃん
数日で黒い毛虫状態から、白っぽいお蚕になっていきます。お蚕を飼うには紙の箱がいいのです。
湿気を一定に保ってくれるからです。
ある程度の湿気がないと、生きていけません

桑の葉・・・蚕のエサ
生まれてすぐから食欲旺盛です。新鮮な桑の葉を常にあげておかなければなりません。
また、桑の葉は多めに入れておくと、
桑の葉が乾燥しにくくなります。
うんちもまだまだ小さく、粉のような状態です。
葉は、上に重ねておきます。
うんちもそのままで、まだかまいません。
5月19日

幼虫から成虫へ
孵化してから2回脱皮し、3令虫になりました。モンシロチョウは孵化すると、卵の殻を食べてしまうし、
脱皮した皮も食べてしまいますが、お蚕は、食べません。
それで、脱皮した皮が、桑の葉にへばりついて残っているので、
脱皮したことが分かります。
お蚕は繭つくりまでに4回脱皮して、どんどん大きくなります。

脱皮・食欲
画鋲の左右、桑の葉にへばりついているのが脱皮した皮です。4回脱皮をしたあとの5令虫は、ものすごい食欲を発揮します。
山のように桑の葉をあげても、数時間で食べつくしてしまいます。
食べて食べて食べ続けるからです。
うんちもあずき大くらい大きなものを,ころっと出します。
そんな様子を子どもたちは面白がって見ています。
また、夜など周囲が静かになると、
お蚕が桑の葉を食(は)む音が雨の降る音に聞こえます。

桑の木
学校には、以前の校長が作ってくれた桑畑があります。桑の木は10本ほどありますが、
用務員さんが手入れをしてくれていて、
質の良い桑の葉が採れます。
しかし、80人近い、3年生が桑の葉を採ると、はげ坊主になってきます。
特に5令虫になると、その食欲はすさまじく、
学校の桑だけでは足りなくなってきます。
近所の桑の木
でも、大丈夫。この桑畑だけでなく、学校の近くにも、
あちこちに、桑の木があるからです。
学校から2~3分のところには、川があり、河川敷に
大きな桑の木が何本もあります。
それもそのはず、かつては、この地でも盛んに
養蚕が行われていたからです。
6月4日

まぶし・・・蚕のマンション
5令虫になって9日ほど(気温や桑の葉のあげ方、個体差にもよる)経つと、いよいよ繭を作り始めます。
桑の葉を食べまくって丸々と大きくなったお蚕は、
体がこれまでの白から透けるような感じになります。
そして上体を持ち上げて、頭の方をゆらしたり、
箱の端っこのほうを、うろうろし始めます。
そのようになったら、まぶしに移してやります。
まぶしとは繭を作るための個室のようなものです。

繭づくり・その1
お蚕は平場では繭を作ることができません。繭を固定するためには壁が必要なのです。
そこで事前に子どもたちにもまぶしを作っておくようにします。
四センチに切った工作用紙を組み合わせて
四センチ×五センチのマスを作るのです。
繭を作り始めるお蚕の体は、少し小さくなります。
そして、まぶしの壁に糸を張ると、繭を作っていきます。

繭づくり・その2
写真の説明を記入します 「頭を八の字に動かして作っている。」と言ったのは「S君」でした。
繭を作っているようすをよおく見ていたから
そのようなことがわかったのです。
透けて見えていたお蚕が
だんだん見えなくなってきました。

繭完成
二~三日で繭が完成します。「小石丸」の繭は小さくピーナッツ型で、糸が取りにくいのですが、
今回の「世紀二一」は大きな繭なので、糸取りがやり易そうです。
しかし「小石丸」は細い、いい生糸が取れます。
小石丸でも三年生が糸取りできますが、
やはり大きな繭の方が見た目がいいのです。

見出し…繭完成
まぶしにきれいに並んだ繭。美しいものです。お蚕はこのシェルター(繭)の中で、さなぎに変身し、
さらに、蚕蛾に変身して、繭から出てくるのです。
モンシロチョウ、アゲハのさなぎは、三年生に見せたので、
お蚕のさなぎもこれから見ることにします。
そのためには、繭をはさみで切り開かねばなりません。
毎回そうですが、 子どもたちは大騒ぎになるでしょう。
6月28日

繭の不思議・・・さなぎ
お蚕は繭というシェルターの中で大変身をします。お蚕のさなぎの姿を見るためには、繭を切り開かなければなりません。
これがなかなかスリリングなのです。
繭の中のお蚕は、お蚕の皮を脱ぎ、まず、さなぎに変身します。
さらに、1週間ほどかかって、蚕蛾に大変身し、
繭から出てくるのです。
繭つくりが終わって数日経った繭を、耳のそばで振ってみて、
カラカラ音がすればちようどいい頃合いです。

繭を切り開く・・・さなぎ
長丸の繭の片方からはさみで切っていきます。切って見えたさなぎが写真のものです。
こわごわ切っている子もいれば、興味深そうにやっている子もいます。
さなぎがふにゅふにゅ動くのを見て、きやーきゃー言う子もいます。
いずれも、秘密のものを見る、不思議なものを見る、
見てはいけないものを見る、といった感じで、興奮気味です。
子こどもたちにはノートにスケッチをさせ、さなぎを切った繭に戻させました何日かでちゃんと蚕蛾になってくれます。

さなぎの不思議・・・変身の理由
さて、完全変態の昆虫は、なぜ「さなぎ」になるのか?幼虫の姿と成虫の姿とでは、全然違うものになるために、
大変身をしなければならないのです。
変身しなければ、、・・・例えばモンシロチョウ、
小さな小さなチョウの姿で生まれたら、
蜜を吸えずに死んでしまうでしょう。
だから、生まれてすぐキャベツの葉を食べられるように、
青虫の姿で生まれてくるのです。自然とは実にうまくできています。

交尾
繭から出てきた蛾は飛べませんが、交尾の相手を求めてバタバタ動き回ります。
繭から出てきた蚕蛾はすぐに交尾をします。
腹がふくれている方がメス、腹のスリムな方がオスです。
蛾は何も食べません。交尾をし、卵を産んで死んでいきます。
子どもたちの育てたお蚕は、すべて蚕蛾にまでさせます。
子どもたちに渡したお蚕は、今年は5匹でした。

産卵・・・卵の産み付け
蚕蛾が、箱から出ないようにして、さらに、給食で出たゼリーのカップをかぶせておきます。
下には新しい画用紙などの紙をしいておきます。
そうすれば、交尾を終えた蚕蛾は、
このカップの中に卵を産んでくれます。
卵を産み付ける紙とカップは、たくさん用意しておき、
子どもたちに渡せるようにしておきます。

来年へ・・・冷蔵庫保管
カップを被せられた蚕蛾は、この写真のように丸く卵を産みつけます。産み付けた紙は、ポリ袋に入れ、理科室の冷蔵庫に入れておきます。
来年の3年生のために。
また、交尾を終え、産卵も終えて死んだ蚕蛾も、回収します。
そして、まとめて埋葬します。
お経をとなえ、学習に役立ってくれたことに、
感謝しつつ埋葬するのです。
南無・・・摩訶般若心経・・・
6月29日

蚕の乾燥死・・・繭の糸取りのために
繭を作ったお蚕の大部分は、糸取りのためにドライアップ(乾燥死)します。
繭を段ボール箱に入れ、布団乾燥機で熱風を送ります。
かなり臭うので、これは外でやります。
数日間かけて、繭の中のさなぎがミイラ状態になるまで乾燥します
ダンボール箱は、閉め切ったままだと熱がこもりすぎて、 乾燥器の安全装置が働いてしまいます。
ですから、箱からはある程度、熱を逃がすようにしてやります。

繭の保存・・・製糸の日まで
こうしてドライアップした繭は、湿気と虫に気をつければ、(防湿防虫剤を入れて)、長い間保存しておくことができます。
これで、いつでも糸取りの授業ができます。
明日、前任校の3年生2クラスで2時間ずつ
糸取りの出前授業をしてきます。
今の学校は、例年かなり後になります。
すぐに糸取りをするようでしたら、冷凍死させてもよいでしょう。
蚕の繭からの糸取りは次の動画でご覧ください。
人間の歴史の授業を創る会
連絡先・事務局
〒340-0802
埼玉県八潮市鶴ヶ曽根824-7
川上泉 方
TEL(FAX): 048-945-0651